一人ひとりが役割を発見し、
持って生まれた能力に気づいて、楽しく働き、楽しく生きよう
一人ひとりが役割を発見し、
持って生まれた能力に気づいて、楽しく働き、楽しく生きよう
目次
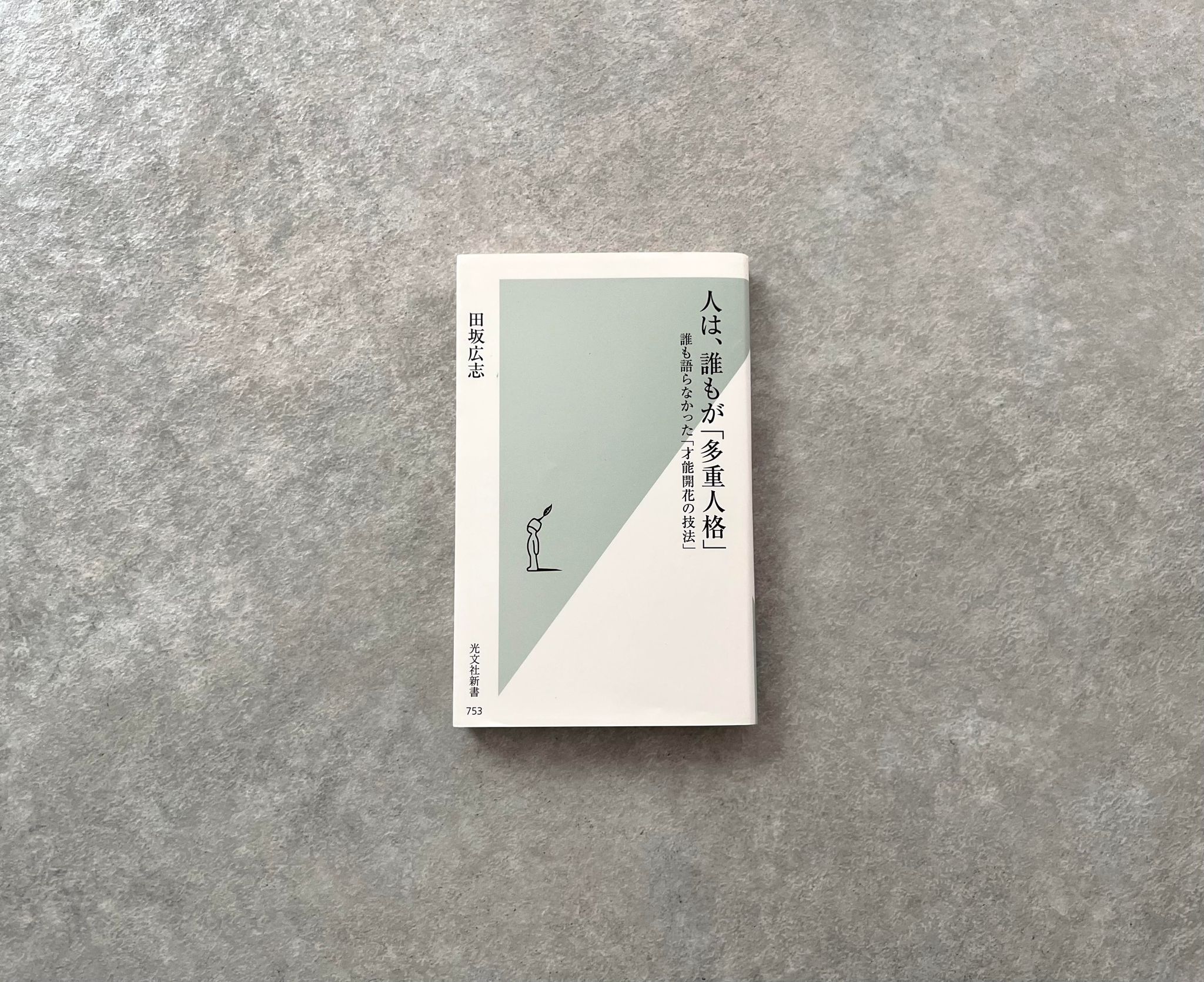
人は、誰もが「多重人格」
誰も語らなかった「才能開花の技法」
田坂広志著
人は、誰もが、心の中に「幾つもの人格」を持った「多重人格」です。
しかし、通常は、仕事や生活の状況や場面に合わせて、
その「多重人格」の中から、ある人格を選び、働き、生活しています。
しかし、自分の中に隠れている「幾つもの人格」に気がつき、
それらに光を当て、意識的に育て、
状況や場面に応じて適切な人格で処することを覚えるならば、
自然に「幾つもの才能」が開花していきます。
それゆえ、自分の中に眠る「幾つもの才能」を開花させたいと思うならば、
自分が意識していなかった「幾つもの人格」に気がつき、
その「多重人格のマネジメント」を行うことが不可欠です。
「多重人格のマネジメント」を行うことによって、
「多様な才能」が開花していきます。
「自分とは何か」という問いは、「自分の中に眠る可能性とは何か」という問いに他ならない。
「自分の中に眠る可能性」を開花することこそが、
まさに「自分とは何か」の問いに答えることであり、「本来の自己」を知ること。
宇宙の歴史とは、宇宙の根源である量子真空が、
「本来の自己」を、次第に知っていくいく過程に他ならない。
この「自分の中に眠る可能性」を開花するための技法を学ぶ内容
7つの知性→思想、ビジョン、志、戦略、戦術、技術、人間力を垂直統合したスーパージェネラリストと呼ぶべき人材が活躍する。7つの知性を垂直統合するためには、置かれた立場と状況に合わせ、自分の中の「様々な人格」を切り替えて対処する「多重人格のマネジメント」が必要(P.8. L.2)
人は誰もが、心の中に「幾つもの人格」を持った「多重人格者」です。
しかし、通常は、仕事や生活の状況や場面に合わせて、
その「多重人格」の中から、ある人格を選び、働き、生活をしています。
しかし、自分の中に隠れている「幾つもの人格」に気がつき、
それらに光を当て、意識的に育て、
状況や場面に応じて適切な人格で処することを覚えるならば、
自然に「幾つもの才能」が開花していきます。
それゆえ、自分の中に眠る「いくつもの才能」を開花させたいと思うならば、
自分が意識していなかった「幾つもの人格」に気がつき、
その「多重人格のマネジメント」を行うことが不可欠です。
「多重人格のマネジメント」を行うことによって、
「多様な才能」が開花していきます。(P.11. L.1)
▶自分の中に眠る可能性(幾つもの才能)を開花させるために、自分の中に幾つもの人格を育てる
演劇のプロフェッショナル、三人目の自分:演じている自分、それを観ている自分、そしてその二人を、少し離れたところから見つめている自分」(P.25. L.1)
経営者は、昔から「多重人格」でなければ務まらない職業。会社のビジョンを語るとき「ロマンと情熱」を持った人格が前面に出てこなければ社員の心に火をつけることはできない。一方、経営会議で経営陣を相手に収益計画の話をするとき「数字の鬼」と呼ばれる厳しい人格が前に出てこなければ、企業の存在さえ危うくすることがあります。若手社員に対しては「優しい親父」、幹部やマネージャーに対しては「強いリーダー」の人格で処する必要があります。(P.26. L.1)
「器の大きな人物」という言葉がありますが、この言葉の本当の意味は「自分の中に、幾つの自分、幾つの人格を持つことができるか」という意味の「器」(P.29. L.1)
我々は、誰もが、自分の中に「複数の人格」を持っている。(P.33. L.4)
自分の中に「複数の人格」を持っていると自覚しているだけで、「多様な才能」が開花していきます。(P.36. L.1)
自分の中にある「複数の人格」を自覚し、置かれた状況や立場によって「異なった人格で対処する」ということを意識的に行うならば、自然に「様々な才能」が開花していきます。その「多重人格のマネジメント」を行うだけで、我々の中に眠っていた「多様な才能」が開花し始めます。(P.36. L.3)
「才能」の本質は、「人格」である。そのことを理解して頂きたいのです。「何々の才能」とは、その大半が、その人物の「人格」や「性格」と呼ばれるもの。~中略~ビジネスの世界や実社会での仕事は何であれ、求められるのは、「人の心」に処する力だからです。すなわち世界で求められる「才能」のほとんどが、「人格」や「性格」と密接に結びついているからです。(P.37. L.1)
「仕事のできる人」とは、「場面や状況に応じて、いろいろな人格を切り替えて対処できる人」~中略~ この人の優秀さの本質は、「業務に慣れている」ことでも、「仕事が速い」ことでもありません。この人の優秀さの本質は、自分の中に「何人もの人格」がいて、状況に応じて「最も適切な人格」が前に出てくることです。その「複数の人格」を瞬時に使い分ける能力があることです。
・時間を気にしているのを感じ取ること→顧客を不快にさせない「温かく親切な人格」
・正確さが求められる操作に向かう時→顧客から信頼を得られる「几帳面で細やかな人格」
・後輩の研修生を指導する瞬間→「厳しくも包容力のある人格」(P.42. L.6)
精神的基礎体力をつける
状況に応じて適切に「人格」を切り替えるということは、かなりの「精神スタミナ」が求められる営みなのです。従って、永年の修行を通じて、その「精神のスタミナ」、「精神的基礎体力」を身につけていないと、頭では「人格の切り替えが大切」と分かっていても、それを現実の場面に合わせて瞬時に「切り替える」ことができないのです。
若い時代から、メール一つ、電話一つでも、細やかに人格の切り替えを行いながら、相手に対応する修行を積むことです。(P.52. L.1)
企画会議のノウハウは「人格」の使い分け
・アイデアやコンセプトを出し合うとき→楽しくリラックスした人格
・出てくるアイデア、コンセプトに対して→寛容で前向きな人格
・出尽くした頃→厳しさと緊張感のある人格、慎重で現実的な人格
※リアリティ・チェック:現実的な観点(リアリティ)からアイデアやコンセプトを厳しく検討(チェック)すること。現実的なものに練り上げていく。
・企画をまとめるために→独裁者
※企画会議の運営ノウハウは、「始め民主主義、終わり独裁」(P.55. L.6)
しなやかな心の本質
ペルソナが硬いという意味は、ある立場や状況で被っている「ペルソナ」を立場や状況の変化に合わせて、柔軟に他の「ペルソナ」に取り換えることができないという意味です。立場や状況の変化に合わせて、一つの「人格」から他の「人格」に柔軟に切り替えることができないという意味です。~中略~ 「才能の開花」という点で見たとき、問題になるのは、「一つの仕事」において、「ペルソナ」が硬い人です。~中略~ 「ペルソナ」が硬いと、本来持っている「様々な人格」のうち、「ペルソナ人格」以外の多くの人格を、深層意識で抑圧してしまうのです。そのため、その抑圧された「様々な人格」に伴う「様々な才能」が、開花できなくなる。
【深層意識】心の奥深くで働く、自分でも気づかない心の動きのこと。普段意識されていない、無意識の心理状態。(P.64. L.5)
才能の抑圧は、必ず、「深層意識」の世界で起こります。この深層意識の世界に「否定的な想念」や「マイナスの想念」があると、人間の能力は必ず、抑え込まれます。なぜなら、「否定的な想念」や「マイナスの想念」は、能力を「萎縮」させてしまうから。(P.73. L.7)
自己限定の意識
「自分には才能が無い」「自分にはできない」という自分の能力と可能性を限定してしまう深層意識。その深層意識が、恐ろしいほどに、我々の才能の開花を妨げてしまいます。
自分の才能を開花させるための問い
自分の中に「多様な才能」が眠っていることを、
自分は、心の奥底で、本当に信じているか?
表層意識では「自分の可能性を開花させたい」と思っていても、深層意識の世界で「自分には才能が無い」「自分にはできない」と思っているならば、その深層の想念が才能を委縮させ、抑圧してしまうため、それを開花させることはできないからです。表層意識でアクセルを踏みながら、深層意識でブレーキを踏んでいる人が多い。(P.78. L.1)
「潜在意識」を変えられない真の理由
表層意識のところに、無理やり「プラスの想念」を引き出すと、深層意識に「マイナスの想念」が生まれてしまいます。~中略~ 表層意識が「できる」と思えば思うほど、逆に、深層意識は「できない」と思っていく。そして、その深層意識が、我々の能力の発揮や、才能の開花を抑えてしまうのです(P.82. L.18)
無意識の言葉の持つ怖さ
「無意識に使っている言葉」こそが、我々の「無意識の世界」に浸透し、強く働きかけている。~中略~ 我々が無意識に使う「言葉」が意図せずして、世界を「プラスの世界」と「マイナスの世界」の二つにわけてしまう。表層意識が語る「肯定的な言葉」の裏に、深層意識の「否定的な言葉」が隠れている。自己限定の深層意識となって、我々の能力の発揮を妨げ、才能の開花を抑えてしまう。(P.87. L.4)
優しい課長の深層意識
部下の気持を感じる力や温かい言葉を語る力はあるが、部下を牽引する力や直観的判断の力は、あまり無い」という自己限定の深層意識が、優しい課長の中に眠る「才能」の開花を妨げてしまう。
▶自分の中に隠れている「様々な才能」を開花させたいと思うならば、自分が被っている「硬いペルソナ」に気づき、その「硬いペルソナ」が深層意識で抑圧してしまっている「隠れた人格」と「隠れた才能」に気づく必要がある。
自分の「硬いペルソナ」の陰に隠れた「様々な人格」の存在に気がつき、それを認め、受け容れることです。もし、それができるならば、それぞれの「人格」に伴う「才能」を、どれも抑圧せず、開花させていくことができる。(P.96. L.2)
マネジメントやリーダーシップの世界では、性格や人格の切り替えや使いわけが求められる理由
マネジメントやリーダーシップの本質が、「矛盾」に処すること
経営者やマネージャー、リーダーの成長とは、ある意味で、その「矛盾」に処することのできる「多重人格者」になっていくということ。~中略~ 深みのある人物とは、多重人格のこと、自身の内に「いくつもの人格」を育てており、場面や状況に応じて、さまざまな人格が適切な形で出てくる、その「人間としての奥行」のようなものを「深み」と評している。
本当に「深い思想」を持った人は、やはり「多重人格」です。そもそも「思想」とは、その思想を「実際に生きた」とき、「真の思想」と呼ぶのであり、ただ、世界中の様々な思想を「単なる知識」として学んだだけでは、「真の思想」を身につけたとは、言えません。
「思想」とは、現実の人生の中で、人間関係の中で、組織の中で、社会の中で、それを「生きる」ために、目の前の現実と格闘したとき、初めて「生きた思想」になり、「真の思想」になる。
【処する】その場に身をおく、対処する。(P.100. L.10)
「多重人格のマネジメント」を適切に行えば、日常の仕事や生活において、これまで隠れていた人格を開花させ、隠れていた才能を開花させていくことができる。(P.112. L.2)
具体的に「多重人格のマネジメント」を行うには、「基本的な技法」、ビジネスメールや電話を使った「人格の切り替え」を実践し、「精神的基礎体力」をつけるだけでも、必ず何かの変化が起こります。~中略~ そうした「基礎的修行」を抜きにしては、次の段階の「高度な技法」を身につけることはできない、その体力が無ければ、ただ、技法を頭で理解しただけに終わってしまいます。※編集有り(P.113. L.1)
「人格を切り替えた」という意味は、「日常の職場で表に出す人格を切り替えた」という意味であり、正確に言えば、「自分の中の『様々な人格』の中から、職場の状況において『表に出す人格』を適切に選ぶようにした」という意味。その通りです。トラブルのとき、「冗談好きで、話好きな、明るい人格」が前に出たのではまずいですね(笑) (P.120. L.4)
「明るい人格が無い」という人は存在しないのです。誰の中にも、可能性としては、「すべての人格」が隠れているのです。なぜなら、世の中に「人格形成」という言葉があるように、我々の「人格」とは、そのかなりの部分が、「生きてきた環境」「出会った人間」「与えられた経験」などによって、「後天的」に「形成」されるからです。従って、環境、人間、経験を適切に選び、時間をかけることによって、本来、我々は、その可能性の中から、自分の意志で、「どのような人格」でも育てていけるのです。(P.121. L.3)
大きな問題は、我々の多くが、自分の「人格」や「性格」について、「親から受け継いだものだから、仕方がない」や「生まれつきこうだから、変えようがない」という「強い固定観念」と「自己限定の意識」を抱いてしまい、本当は、自分の中に、新たな「人格」や「性格」を育てることができるという事実を理解していないことです。(P.123. L.3)
人格は「変える」のではなく「育てる」
現在の人格を「変えよう」とせず、新たな人格を、自分の中に「育てる」ことです。~中略~「怒りやすい人格」を「寛容な性格」に「変える」ことは至難の業です。抑圧して自分の中から「消し去った」と思い込んでも、実際には、心の奥深くに押し込んだだけで、消えていませんから、何かの拍子に、その「怒りやすい人格」が、突如、表に出てきて「爆発」することになります。特に、強く「抑圧」すると、強く「爆発」することになります。(笑)ただ、その「怒りやすい人格」にも、ときおり、「出番」を作ることが必要です。周囲に被害を与えない形での「出番」です。(笑)この修行を続けていると、自然に、その「出番」をつくる「もう一つの人格」が現れてきます。「役者」に出番を指示する「舞台監督」のような人格です。(P.124. L.1)
人格を「演じる」ことは、人格を「育てる」こと
「ある人格を演じる」ということと、「ある人格を育てる」ということは、同じことなのです。ある人格を、気持ちを込めて「演じて」いると、その人格が、自然に「育って」くる。我々は、「様々な人格」を育てることができるのであり、我々の中には、可能性として「すべての人格」が隠れているのです。多重人格のマネジメントの技法を修得するためには、まず無条件に「自分の中には、すべての人格が隠れている」と思いを定めて頂きたいのです。なぜなら、その思いを定めることが、自分の中に隠れている「様々な才能」を開花させるための、極めて大切な心構えになるからです。(P.128. L.9)
「才能の本質は、人格」だからです。従って、「自分の中には、すべての人格が隠れている」と思いを定めることは、「自分の中には、すべての才能が隠れている」と思いを定めることと、同じことなのです。
逆に言えば、「自分の人格は、これだけだ」と思ってしまうことは、「自分の才能は、これだけだ」と思ってしまうことと同じであり、その結果、「自己限定の深層意識」が生まれてしまい、「才能の開花」を抑えてしまうのです。(P.130. L.2)
「隠れた人格」の三つのレベル
「表に出したい人格」がどのレベルの「隠れた人格」かによって技法の難しさが違ってきます。
第一は、「表層人格」
ある状況では隠れていますが、他の状況ではすでに表に出ている人格です。例えば、友人関係では「話好きな、明るい人格」は、職場では無意識に抑圧していたため、表に出ていなかった人格であり、表層人格の事例です。
第二は、「深層人格」
現在は隠れており、表に出てきていない人格ですが、置かれている立場や状況が変わったり、意識的な努力をすることによって、自分の中に育ち、表に出てくる人格です。例えば、「父親らしくなってくる」という親に甘えてばかりの自立心の無かった若者が、結婚して子供を授かり、親としての自覚が芽生えてくると、「らしくなる」。立場が変わったことによって、「父親人格」や「母親人格」が自分の中に育ち、表に出てきたのであり、世の中で、しばしば見られる「深層人格」の事例です。
第三は、「抑圧人格」
何かの理由で、強く抑圧されており、心の奥底に抱え込まれ、なかなか表に出てこない人格です。例えば、幼少時に親から虐待され、甘えることが許されなかったため、強く抑圧してしまった「他社に甘える人格」などが、その一つの事例です。
「隠れた人格」がどのレベルかによって、それを開花させ、活用する技法が変わってくる。(P.131. L.1)
第一の「表層人格」を開花させる技法
1.自分が、今の仕事に「どのような人格」で取り組んでいるかを、自己観察する。
我々は、意外に、自分が、どのような「人格」で仕事に取り組んでいるかを知らないからです。
例えば、この人は「営業担当者は、お客様に明るく応対」といったステレオタイプの営業担当者像を固定費観念にしてしまっているのです。もしこの人が仕事のできる営業担当者であるならば、間違いなく「明るい性格」だけでなく、「細やかな性格」でも仕事をしています。お客さまの何気ない表情を読む、言葉の奥の心の動きを感じ取るなどの「細やかさ」という才能を発揮しています。営業のプロフェッショナルとして一流の世界を目指すならば、「明るい性格」よりも、むしろ、この「細やかな性格」をさらに磨いていくことが王道なのですが、自分の中にある「細やかな性格」に気づかないかぎり、この性格や人格を意識的に育てていくことはできないのです。自分でも気がついていない「人格と才能」は、育てようがない。優れた上司であるならば、「誉め言葉」を通じて、この「気がついてない人格」に気がつかせてくれるでしょう。「君の、あの細やかな気配りはさすがだな」「お客様は、言葉にしなくとも、君が気持ちを汲んでくれるので、喜ばれていたな・・・」。部下に対する「誉め言葉」は、単に「部下のモチベーション」を上げるためにあるのではなく、本来、「部下の成長」を支えるためにある。残念ながら、最近のマネジメント論は、「いかに部下のモチベーションを上げるのか」といった操作主義的な傾向が強いので、部下の成長を支えられる上司が育たないのですが。
▶「自分が、いまの仕事に『どのような人格』で取り組んでいるかを、自己観察する」ことが第一の技法。
2.自分が、仕事以外の世界で、「どのような人格」を表しているかを、自己観察する。
家族との関係、友人との関係、恋人との関係で現れる人格などです。それぞれの関係において、自分の中の「どのような人格」が表に表れているかを自己観察してみることです。それぞれの関係において、かなり違った自分が表に出ていることに気がつくでしょう。その自己観察を通じて、自分の中に、どのような人格があるかを、一度、深く見つめてみることです。
持っている人格を前に出さない理由
人格を抑圧してしまう「自意識」
・職場でこういう人格を出すと周りから誤解されるのではないか
・評価が下がるのではないか
・自分を優秀に見せたい、格好よく見せたい表層人格であるのにもかかわらず、場面で表せないのは不器用さではなく、「基礎体力が無い」
「人格の切り替え」ということは、単に一つの人格からもう一つの人格に切り替えるという行為ではなく、「これまで表に出していた人格」にこれまで表に出していなかった人格」を加えて、それら「複数の人格」を状況に応じて適切に使い分けるという行為なのです。
そのため、それを実際に行おうとすると、「置かれた状況の判断」「周囲の人間の心境の感知」「適切な人格の選択」「自然な人格の切り替え」という一連の作業を、瞬時に行う必要があり、それには、相応の集中力が求められるのです。それは、言葉を替えれば、「精神的基礎体力」、すなわち、「精神のスタミナ」が求められる行為なのです。(P.140. L.5)
「精神のスタミナ」が高いレベルにあるということは、分野を問わず、「仕事ができる人」の基本的な条件であり、「一流のプロフェッショナル」への絶対的な条件。(P.142. L.7)
3.「仕事ができる人」が、仕事でどのように「人格」を切り替えているかを、観察する
一流のプロフェッショナルは、一つ二つの「技」で、その高度な力を発揮しているわけではない。様々な「技」の、全体のバランスによって力を発揮している。
4.自分の仕事において、表に出して活用する「人格」を、切り替える
「人格」というものを意識して育てる。意識して育てる「隠れた人格」
営業の仕事を通じて、「気を利かせる」「気を配る」「気を使う」という修行を積んでいるとやはり、それなりに「気の利く性格」が、自分の中に育ってくるのですね。
●「深層人格」を開花させる方法(3つの技法)
1.優れたプロフェッショナルを「師匠」として、その「師匠」から「人格」を学ぶ
誰もが持っていながら開花せずに終わっているのが、この「リーダーシップ人格」この人格は、ある状況や立場に置かれると、自然に開花する人格。
この上司についていけば、自分が決めなくてもという依存心が、彼の中の「リーダーシップ人格」の開花を妨げていた。
立場が人を育てる、立場が人格を引き出す
「自分の個性」に突き抜ける時代 個性に突き抜けるという段階
師匠から学んだ「人格」が、自分の他の「人格」と影響を与え合い、ときに融合し、自分らしい個性的な「人格」に突き抜けていきます。
子供の成長のプロセスにおいては、「個性」とは、「枠に嵌めないで、自由に思考し、行動させる」ことによって育つと、言われますが、
プロフェッショナルの成長のプロセスにおいては、「個性」とは、「強大な個性」との格闘を通じて磨き出されるものです。その「強大は個性」とは、「優れた師匠」の示す「強烈な人格」という形で目の前に立ち塞がることも多いのです。(P.162. L.2)
2.自分の中の「隠れた人格」が開花する仕事を選ぶ
端的に言えば「苦手な仕事」、「自分の性格に向いていない」と思う仕事です。
これらに取り組むことは、必然的に、自分の中の「隠れた人格」を開花させることになる。(P.165. L.2)
「苦手」と思う仕事も「不遇」と思う時代も、捉え方によっては、それまで自分の中に眠っていた「人格と才能」を開花させる、絶好機なのです。「前向き」な気持ちで取り組んでいると、実は、どのような仕事も「面白く」なってくるのですね。実は、「苦手な仕事」が与えられたとき、それを「苦痛」と思うかどうか・・・そこが分かれ道なのです。(P.170. L.5)
適性検査が、「自己限定の深層意識」を生み出してしまうという落とし穴
「自分は明るい性格なので営業に向いてる」という肯定的な意識と同時に、「自分は、緻密な性格ではないので、経理には向いていない」という否定的な意識や自己限定の意識があるからです。~中略~ 「私は技術屋ですから」という肯定的な意識の奥底に、「私は事務屋でないから」という否定的な意識が生まれるという怖さですね。(P.174. L.10)
「適材適所」という言葉の怖さ
「適材適所」や「長所を伸ばす」と言った言葉も、その理解や使い方を誤ると、部下の心の中に、「自分は、この場所では、適材ではない」や「これは、自分の短所だ」という裏返しの「否定的な意識」を植え付けてしまい、結果として、その「隠れた可能性」を引き出すことができないマネジメントに陥ってしまうこともあるのです。
3.「日常とは違う場」で表れる「日常とは違う人格」を体験する。
日常的な人間関係の中にいるかぎり、「深層人格」は、なかなか表に出てきません。
日常とは違う場を「経験する」のではなく、「体験する」のです。一日、生活や仕事をしていれば、誰でも、何かの「経験」はしています。しかし、その「経験」を、心の中で振り返り、深く見つめ、そこで何を学んだかを反省すると、それは「体験」と呼ぶべきものに深まっていきます。
正確に言えば、「体験」するのは、その「場」を体験するのではなく、自分の中の「人格」を体験するのです。ある「日常とは違った場」おいて表れてくる、自分の中の「日常とは違う人格」に気がつき、静かに、そして、深く、見つめるのです。~中略~ いったい誰が見つめるのか?それが、「出番」を作る「もう一つの人格」であり、「自分を見つめている自分」と呼ぶべき「もう一つの人格」です。(P.178. L.8)
「日常とは違う場」において「日常とは違う人格」が現れてくることだけでなく、その人の人格を見つめている、「もう一つの人格」が現れてくることだからです。~中略~ 「自分を見つめている自分」と呼ぶべき「もう一つの人格」が現れてくることが、「多重人格目ネジ面と」おいては、極めて重要なのです。いや、それは「才能の開花」という次元を超えて、「人間性の開花」と言えるほど、重要なことなのです。(P.182. L.3)
人間としての「深み」や「成熟」を感じさせる人物は、この人物がそれらの体験を通じて、自分の中の「日常とは違った様々な人格」を体験し、自分の中にある「多様な人格」を深く理解しているからです。そして、さらに重要なことは、それらの「様々な体験」を通じて、自分の中の「多様な人格」を静かに見つめる「もう一つの人格」、すなわち、「静かな観察者」と呼ぶべき人格が、心の中に生まれてきているからです。人間の「深み」や「成熟」とは、その「静かな観察者」が心の中にいることでもあるのです。~中略~ 「自分が見えてない」状態に陥っても。すぐに「静かな観察者」が現れ、「自分が見えている」状態に戻れる。(P.183. L.3)
ある人物の心の奥底に、その「静かな観察者」がいるか、いないかは、「人間的力量」が無ければ、わからない。ある程度の力量があれば、ある人物の心の奥底に「静かな観察者」がいるかどうかは、その雰囲気でわかります。それは「静寂観」。自然に、不思議な「静寂観」を醸し出します。その「静寂観」とは、この日本では「香り」と呼ばれたものですね。「香り」のある人物とは、「静寂観」のある人物を評する言葉。心の中に「静かな観察者」がいる人物であり、「自分が見えている」人物でもあると。「静かな観察者」が心の中にいる人は、不思議なことに、騒いでいても、何かの「静けさ」を感じるのです。(P.185. L.7)
「静かな観察者」とは、丁度、色々な個性の俳優がいる舞台の袖で、静かに劇の進行を眺め、どの場面で、どの俳優が前に出て演技をするべきかを、そっと指示する「舞台監督」のような存在であるとも言えます。~中略~ さらに大切なのは、それを醒めて見ている「静かな観察者」が現れ、育ってくることなのです。「醒めて見ている」とは、自分の中に現れてくる「様々な人格」を抑えもせず、煽りもせず、否定もせず、肯定もせず、ただ、静かに見ているという意味です。逆に、心の中で、「ああ、こうした人格が出てはいけない」といった否定的な気持ちが動くと、その「深層人格」を、心の奥に抑え込んでしまいます。「静かな観察者」という「舞台監督」は、色々な個性の俳優の、誰にも肩入れせず、遠ざけず、その場面で、どの俳優が、どう処するかを、ただ静かに判断し、示唆していく存在なのですね。そして、この「静かな観察者」が、心の中に現れ、育っていくことは、「才能の開花」だけでなく、「人間性の開花」という点でも、とても大切な意味を持っているのです。この「静かな観察者」が心の中に生まれてくると、自分の「エゴ」が見えるようになってくる。(P.197. L.2)
「抑圧人格」が生まれてくる原因
残念ながら、「抑圧人格」を表に出し、開花させる容易な方法はありません。もともと「抑圧人格」とは、何かの理由で、強く抑圧し、心の奥深くに押し込んでしまっている人格なので、通常の技法ではそれを表に出すことができない。おこなうならば、心理療法に基づくカウンセリング、セラピーなどの技法を用いる必要があります。※「抑圧人格」を開花させる技法をここでは述べない。
なぜ、自分の中にある「特定の人格」を抑圧してしまのかについて、3つの原因を述べたいと思います。
1.その人格が、「社会的な倫理や禁忌」に触れると思われる場合。(例:同性愛を好む人格)「~してはならない」という表層的意識によって強く抑圧されてきました。
2.「過去の経験のトラウマ(心的外傷)」です。過去に、ひどい恥辱や深い喪失など、「思い出したくないほどの痛苦な経験」がある場合、「その経験に付随する人格」を無意識に抑圧してしまいます。
3.「他社に対する嫌悪」です。例えば、過去において、誰か他人の中に見た「嫌な人格」を、自分の中にも感じるとき、それを無意識に抑圧してしまうことが起こります。厳格な父親の下で育った息子が、奔放な生き方をする、といったことは、この例に当てはまることが多いですね。
1と2の原因となる人間の心の動きを理解すると、人間心理についての、一つの「逆説的な真実」に気がつきますね。「他社への嫌悪の本質は、自己嫌悪である」。その真実です。「他社への嫌悪」のすべてが、この「自己嫌悪」であるとは思いませんが、自分の中にある「好きになれない人格」を抑圧していると、他人の中にその「好きになれない人格」を見たとき、嫌悪感が増幅されるのですね。従って、「他者への嫌悪の本質は、自己嫌悪である」というのはしばしば真実なのですね。そしてこの「逆説的な真実」に気がつくとき、世の中にある。あの言葉の深い意味が分かってくるのです。「自分を愛せない人間は、他社を愛せない」この言葉は、自分の中に「自己嫌悪」を抱えているかぎり、人を好きなることはできない、という意味でもあるのですね。(P.200. L.1)
「隠れた人格と才能」を開花させる技法を実践するとき、これらに並行して、さらに二つ、実践するべき技法があります。それが、「豊かな人間像と人間性」を開花させる技法です。
●「豊かな人間像」を開花させる技法
自分の中に「多様な人格」を育てたいと思うのであれば、自分の中に「多様な人間像」を持っているかが問われます。「豊かな人間像」を持っているかが問われます。自分の中に「貧しい人間像」しか持たなければ「多様な人格」を開花することはできません。
このような言葉遣い 「しょせん、人間なんてものは・・・」こうした言葉遣いの背景には、貧しい「人間像」があるのですね。そして、我々がこうした「貧しい人間像」を持つかぎり、その人間像の中での「自己限定」となって、「多様な人格」の開花を妨げるのですね。
どうして、我々の「人間像」が貧しいものになってしまうのか?
敢えていえば「世界が狭い」、極めて均質な「人間像」しか学べない。世界全体の人種の違い、民族の違い、風土の違い、歴史の違い、文化の違いから形成される、様々な「人間像」の広がりと深みから見れば、我々は、極めて均質な「人間像」しか見ていないのですね。「似たもの同士のコミュニティ」染まってしまい、気がつけば、極めて貧しい「人間像」しか身につけていないような気がする。本来もっとも望ましいことは、「様々な人生経験」を積むこと。しかし、直接的に「人生経験」の幅を広げることは時間的な制約や経済的な制約もあり、限界があるため、「教養」を身につけること。本来「教養」という言葉の一つの大切な意味は、「豊かな人間像」や「深い人間観」を身につけることにあります。その本来の意味での「教養」を身につけることです。かつてその役割を担っていたのが「文学」です。その小説の主人公の生き方や心の動きを通じて「人間像」を広げ、「人間観」を深め、真の「教養」を身につけるためだった。最近では、活字離れが進み、「純文学」や「古典文学」を読む文化は失われてしまっていますが、代わるものとして「映画」。映像や画像、音声や音響などのマルチメディアを使った伝達であるため、その「物語」を高度なレベルで「疑似体験」できるのです。最も大切なものは、「人間像」や「人間心理」をリアルに描いた「優れた原作や脚本」、そして「優れた役者の演技」と「優れた監督の演出」の3つでしょう。
映画を観るとき、登場人物の置かれた状況を見て、「自分が、この状況だったら」と考えることは、「人間心理」を学ぶ一つの優れた技法であり、「人間像」を広げ、「人間観」を深め、日常では気がついていない「別の人格」を発見する技法になると思います。「共感」とは、「相手の姿が、自分の姿のように感じられる」という感覚です。心理学用語で言えば、相手の中に「可能的自我」を見ることです。すなわち、「共感」とは、「相手が示す、そのような人格は、自分の中にもあるのではないか」という感覚とも言えます。
「悪人」を演じるときは、その人間の「善き部分」を見つめて、演じよ。
「善人」を演じるときは、その人間の「悪の部分」を見つめて、演じよ。
我々の人間としての成長と成熟のためには、優れた映画と演技を通じて、「悪人」の姿や心を見つめることも極めて大切なのですね。なぜなら、「悪人」の示す「悪の部分」や「弱き部分」は、実は、人間であるかぎり、誰の心の中にもあるからです。
昔から、経営の世界で語られてきた格言に、「経営者として大成する人間は、悪いことができて、悪いことをしない人間だ」という言葉がありますが、人間としての成長と成熟のためには、「自分は善人だ」という素朴な自己妄想を抱いて歩むのではなく、自分の中の「悪の部分」を見つめることも、大切な意味があるのですね。そして、その「悪の部分」を知っているからこそ、それに流されない「強さ」も生まれてくるのですね。
優れた「原作や脚本」「役者の演技」「監督の演出」の三つが揃った映画、登場人物の「人間」をリアルに描いた映画を選んで観るならば、そして、名優が演じるその登場人物に深く「感情移入」し、「共感」し、「自分が、この状況だったら」「自分が、この登場人物だったら」と考えながら観るならば、それは「人間心理」を学び、「人間像」を広げ、「人間観」を深め、日常では気がついていない「別の人格」を発見する、一つの優れた技法になるでしょう。
●「豊かな人間性」を開花させる技法
「多重人格のマネジメント」を実践すると、なぜ、「豊かな人間性」が開花するのか、その「三つの理由」を述べておきましょう。
1.「相手を理解し、相手の気持ちが分かるようになる」からです。
すなわち、「多重人格のマネジメント」によって、自分の中に「様々な人格」が開花していくと、他の人の「人格」を理解できるようになり、そうした人格を持った人の「気持ち」がわかるようになるのです。
2.「相手の状況や心境に合わせて、適切な人格で対処できる」からです。
すなわち、相手の人格、相手の状況、相手の心境を、瞬時に判断し、その場で、最も適切な人格を前に出すことができるようになります。仏教に「対機説法」という言葉がありますが、相手の「機」や「機根」に応じて、話の内容を変えるという説法のやり方です。
3.自分の中に「様々な人格」が開花するだけでなく、自然に、それらの人格を静かに見つめている「もう一つの人格」、すなわち、「静かな観察者」が生まれてくるからです。
「静かな観察者」が重要な理由は、「エゴ・マネジメント」のためです。
「エゴ」とは、我々の心の中の「自我」のことですが、我々が、自らの「人間性」を高めていこうと思うならば、自分の心の中の「エゴ」を適切にマネジメントする必要があるのです。なぜなら、我々が相手を傷つけたり、人間関係を壊してしまうのは、ほとんどの場合、この「エゴ」の動きが原因となるからです。
たとえば、見栄、虚栄心、不信感、猜疑心、嫌悪感、憎悪、不満、恨み、妬み、嫉み、軽蔑、敵意といった「否定的な感情」は、すべて、心の中の「エゴ」が生みだしているものです。我々は、心の中の「エゴ」を捨て去ることはできないのですね。我々が、本当に「エゴ」を捨て去ったならば、生きていくことはできないでしょう。そして「エゴ」は、表面に出てこないように抑えても、必ず、別なところで形を変えて、表に出てきます。この厄介な「エゴ」の動きに処する方法は、実は、ただ一つです。ただ、静かに見つめる・・・。それだけです。ただ、静かに見つめる。それだけで、不思議なほど、「エゴ」の動きは静まっていきます。決して消え去っていくわけではない。「静かな観察者」が「エゴ・マネジメント」において大切になる。
長期的視点で見るならば、心の中の「エゴ」に対しては、実は、もう一つ、大切な処し方があるのですね。「エゴ」を育てること。我々の心の中の「エゴ」を「小さなエゴ」から「大きなエゴ」へと、育てるのです。
「小我」から、「大我」へ
この言葉は、人間の心の中の「小さなエゴ」(小我)を無くすことはできない。さればその「エゴ」を「大きなエゴ」(大我)へと育てていくべきだと、教えています。
我々は、誰もが、無意識に、自分の心の中の「小さなエゴ」を「大きなエゴ」に育っているのですね。自分だけを見つめている「エゴ」から、部下を見つめるように、社員全体を見つめるように、「自分のエゴ」を部下や社員を包み込んだ「大きなエゴ」へと育てているプロセスなのです。なぜなら、この「自分のエゴ」にとっては、「部下を幸せにする」ことも、「社員全員を幸せにする」ことも、「自分の喜び」であり、「自分の幸せ」だからです。その機微を、昔から仏教では、「自利は、利他なり。利他は自利なり。と教えている。「大きなエゴ」は、他人の幸せを自分の幸せと感じられる「エゴ」ですので、周りの人間や会社全体、さらには、社会全体に、良き影響を与えていくのですね。
「小我」を「大我」への育てていくと、「大我」は、「無我」に似たり。
「小我」を「大我」への育てていくために、人生において、「志」や「使命感」を持って、生きることです。
自分のささやかな人生を、世の中のために、多くの人々の幸せのために、使いたい。
その「志」や「使命感」を持つことです。
そのときに、我々の中の、「自分」だけを見つめる「小さなエゴ」が、仲間を見つめ、社会を見つめ、世界を見つめる「大きなエゴ」への成長の道を歩みはじめるのですね。そして、我々の中の「小我」が、「大我」へ育っていくのですね。
条件を実現するための七つの身体的技法
①呼吸を整え、深い呼吸を行う
②音楽の不思議な力を活用する
③群衆の中の孤独に身を置く
④自然の浄化力の中に身を浸す
⑤思索のためだけに散策をする
⑥瞑想が自然に起こるのを待つ
⑦全てを託するという心境を祈る
①まず、一度、自分の考えを「文章」に書き出してみる
②心の奥の「賢明なもう一人の自分」に「問い」を投げかける
③徹底的に考え抜いた後、一度、その「問い」を忘れる
④意図的に「賢明なもう一人の自分」を追い詰める
⑤ときに「賢明なもう一人の自分」と禅問答する
⑥一つの「格言」を、一冊の「本」のように読む
⑦思索的なエッセイを「視点の転換」に注意して読む
・偏差値によって人間を格付けしてしまう現代の教育で意識に刷り込まれたもの
・人間を勝ち組と圧倒的に多数の負け組に分けてしまう競争社会が意識に浸み込ませてしまった
ものにすぎない(田坂広志氏)
自己限定を払拭するために
・自己限定の意識が「刷り込まれた幻想だった」と気づけば、自分でも信じられないほどの才能や能力が開花する。
私たちの中には想像を超えた素晴らしい才能や能力、可能性が眠っている。
①人間の可能性を信じること
②天才の秘密を知ること
③自己対話の技法を実践すること